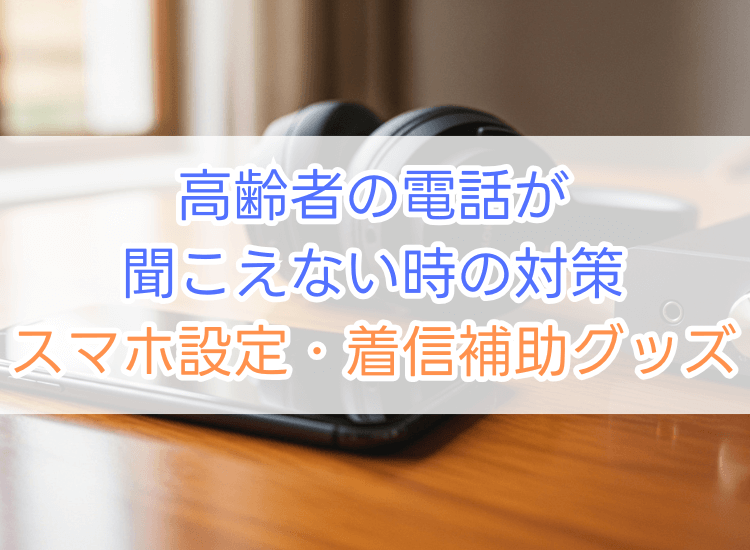高齢者がスマホの電話になかなか気づかなかったり、通話中の声が聞き取りにくかったり…
そんなお悩み、意外と多いのではないでしょうか。
「高齢の親の電話が聞こえないみたい…」「スマホの着信音を大きくできないかな?」と対策を探しているあなたへ。
この記事では、着信に気づきやすくなるスマホの設定方法や、光や振動で知らせてくれる便利なグッズ、さらには各携帯キャリアが提供している耳が遠い方向けの電話やサービスについて、わかりやすく解説していきます。
どうして着信に気づきにくいのか、その理由から具体的な解決策まで、公的な情報をもとに、まるっとご紹介しますね。
高齢者の電話聞こえない時の対策【スマホ】|原因と基本対策

- 高齢者はなぜ着信に気づきにくい?
- 高齢者向けスマホ着信音を大きくする方法
- スマホ着信に気づかない時の対策
- スマホ着信お知らせグッズ【高齢者向け】
- 携帯電話の着信を光で知らせる
- 高齢者・難聴向けの携帯電話
高齢者はなぜ着信に気づきにくい?
スマホの着信に気づきにくくなるのには、実はいくつかの理由が重なっています。
耳の聞こえ方だけでなく、毎日の生活音やスマホ自体の設定も関係しています。
まず知っておきたいのが、年齢とともに起こる「聞こえ」の変化です。
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会によると、年を重ねるにつれて高い音(高音域)から聞こえにくくなり、65~74歳では約3人に1人、75歳以上では半数近くの方が難聴に悩んでいるそうです。出典:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
スマホの着信音は、この高音域の音が中心になっていることが多いため、鳴っていても「音として認識しにくい」ということが起こりがちなんです。
専門的に言うと、耳の奥にある「蝸牛(かぎゅう)」という部分の細胞が、年齢とともに少しずつ減ってしまうことが原因とされています。
この細胞は音の振動を電気信号に変える大切な役割を担っていて、特に高い音に影響が出やすいんです。
だから、ベルや電子音のような「キーン」という甲高い音が、弱く感じられてしまうんですね。
このタイプの難聴だと、音量だけでなく言葉の聞き取りも難しくなるので、「何かが鳴っている」「話している内容がわからない」といったことに気づきにくくなります。 出典:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
次に、私たちの生活環境も意外と見過ごせません。
テレビの音、台所の換気扇の音、外を走る車の音…。こうした生活音に、か細い着信音が「かき消されてしまう」ことがあります。
特に高い音は周りの音に埋もれやすいので、「バイブだけじゃ気づけない」「ちょっと離れた場所に置いたら聞こえなかった」なんてことがよく起こるんです。
スマホの置き場所や持ち方も大切です。クッションや布団の上、バッグの奥深くなど、音や振動を吸い取ってしまう場所に置くと、せっかくの着信音やバイブレーションが弱まってしまいます。
寝るときに枕の下に入れていると、ブルブルという振動が布に吸収されて、ますます気づきにくくなります。
さらに、スマホの初期設定が、高齢の方の聞こえ方に合っていないこともしばしば。
例えば、着信音量が小さめだったり、光で知らせてくれるLEDフラッシュ通知がオフになっていたり、バイブレーションが弱かったり…。
これでは、気づくチャンスそのものが減ってしまいますよね。
iPhoneなら設定からLEDフラッシュをオンにすれば、ロック中に背面のライトがピカッと光ってお知らせしてくれます。出典:Apple
Androidでも最近は「点滅による通知」が標準で使えるようになっているので、光の力を借りることができますよ。 出典:Google
着信に気づけない問題は、たった一つの原因ではなく
- 聞こえの変化(高い音が苦手になる)
- 生活音との重なり
- スマホ設定のミスマッチ
という3つの層で考えると分かりやすいです。
だから対策も、この3つの層に合わせて行うのが効果的です。具体的には
- 「音」
高音だけでなく、低~中音域の聞きやすい音に変えて、音量をしっかり確保する - 「光」
LEDや画面の点滅で目で見てわかるようにする - 「振動」
スマホ本体だけでなく、腕時計型の端末や振動クッションなどをプラスする
という、複数の方法で気づけるように準備しておくのがおすすめです。
これに加えて、「いつもここに置く」という定位置を決めるだけでも、見逃しはぐっと減りますよ。
周波数とは?
周波数(Hz)は音の高さを表す単位で、数字が大きいほど甲高い音です。
高齢者になると高い音から聞こえにくくなる傾向があります。
分かりやすく言うと、電子音やベルの「チリン♪」という高い音よりも、少し低めの「ブーッ」という音の方が気づきやすいことがある、ということです。
高齢者向けスマホ着信音を大きくする方法
音量ボタンを最大にしても「なんだか聞こえにくい…」という時は、音量以外の部分も見直してみましょう。
年齢とともに高い音が聞き取りにくくなることを考えると、音色(トーン)を変えるだけで、同じ音量でもぐっと聞きやすくなることがあるんです。
甲高いベルの音よりも、低め~中くらいの音を含むブザー音やチャイム音、リズムがはっきりした曲などに変えてみるのが第一歩。
ほとんどのスマホには、初めからいくつかの着信音が用意されているので、実際に聞きながら選んでみてください。
iPhoneの基本設定とコツ
iPhoneでは、「設定」→「サウンドと触覚」を選ぶと、着信音の変更や音量調整ができます。
もし本体横のボタンを押しても着信音量が変わらない場合は、「ボタンで変更」という設定がオフになっているかもしれませんので、チェックしてみてください。出典:Apple
あわせて、LEDフラッシュ通知をオンにしておくのがおすすめです。
着信があったときに、本体の背面ライトがピカピカっと点滅するので、音を聞き逃しても目で見て気づけます。
設定方法は「設定」→「アクセシビリティ」→「オーディオ/ビジュアル」→「LEDフラッシュ通知」です。 出典:Apple
Androidの基本設定とコツ
Androidは機種によって少し違いますが、基本は「音、バイブレーション」といった設定項目から、着信音・通知音・通話音量をそれぞれ調整できます。
本体の音量ボタンは、電話中や動画再生中など、状況によって調整する対象が変わってしまうことがあるので、設定画面から直接スライダーを動かすのが確実です。 出典:Google
目で見てわかるようにするには、Androidの「点滅による通知」が便利です。
この機能があるスマホなら、カメラのフラッシュや画面自体がピカッと光って、電話やメッセージを知らせてくれます。
光る色を選んだり、どんな風に光るか試したりもできますよ。出典:Google
スマホメーカー独自の工夫も役立ちます。例えば、Galaxyのスマホにある「Edge lighting」という機能をオンにすると、画面のフチがふんわり光って通知を教えてくれます。出典:Samsung
音の「届き方」も工夫しよう
音色や音量を調整したら、今度は音の「出口」と「置き場所」もチェックしてみましょう。
スマホケースがスピーカーの穴をふさいでいませんか?
机にペタッと置くと、音が反射しにくくて弱まってしまうことも。
リビングや台所など、いつもいる場所の近くの棚の上を定位置にしたり、Bluetoothスピーカーを別の部屋に置いて家中に音を届けたりするのも効果的ですよ。
ポイント
Androidの「通知チャンネル」という機能を使うと、アプリごとに音量や着信音を変えられます。
例えば「大事な連絡用のアプリだけは大きな音で光らせる」といったようにメリハリをつけると、より気づきやすくなりますよ。出典:Android(Google)
スマホ着信に気づかない時の対策
着信を見逃してしまうのは、聞こえの問題だけでなく、生活している環境やスマホの設定も大きく関係しています。
だからこそ、「音・光・振動」という複数の方法を組み合わせ、さらに「スマホの置き場所」と「普段の生活動線」を考えることがとても大切。
こうすることで、周りがうるさくても、別の部屋にいても気づける、頼もしい「お知らせシステム」を作ることができます。
スマートウォッチや活動量計を活用
まず試してほしいのが、スマートウォッチや活動量計といった、手首につけるタイプのガジェットです。
スマホと連携させておけば、電話がかかってきたときに手首でブルブルっと強く震えて教えてくれます。
これなら、スマホがバッグの中や別の部屋にあっても、確実に見逃しません。
Apple WatchやFitbitなど、多くの製品がこの機能を備えていて、設定も簡単。
水に強いタイプも多いので、家事をしているときでも安心です。
スマホの振動(バイブレーション)を工夫する
多くのスマホでは、振動のパターンや強さを変えられます。
例えばiPhoneなら、「設定」→「サウンドと触覚」→「バイブレーション」で、自分だけのオリジナル振動パターンを作ることも可能。
これを使って、メッセージやメールとは違う、特別なブルブルを着信に設定すれば、すぐに「電話だ!」とわかります。
置き場所を固定する
置き場所を決めるのも、とてもシンプルで効果的な方法です。
寝るときは枕元のサイドテーブルに、日中はいつも目に入るテーブルの上などに固定するだけで、音や光、振動のどれかに気づく確率がぐっと上がります。
反対に、ポケットの奥やソファのクッションの下、布団の中などは、音も振動も吸収されてしまうので要注意です。
その他確認しておきたいこと
スマホの「集中モード」や「おやすみモード」の設定も見直してみましょう。
これがオンになっていると、着信や通知が知らされないことがあります。
さらに、料理中や掃除中、テレビを見ているときなど、生活音が大きくなる時間帯には、光や振動の割合を増やす「時間帯別のお知らせ戦略」も有効です。
Androidの「ルール」機能、iPhoneの「集中モードのスケジュール」を使えば、時間に合わせて自動で設定を切り替えられます。
ぜひご家族と一緒に「着信テスト」をしてみてください。
実際に電話をかけてみて、どの方法が一番気づきやすいかを確認するのです。
こうして、ご本人にぴったりの方法を見つけることで、電話の見逃しをゼロに近づけることができますよ。
スマホ着信お知らせグッズ【高齢者向け】
スマホの設定を変えるだけでなく、外付けの便利なグッズを使うのも、着信の見逃しを防ぐとても良い方法です。
特に、耳が聞こえにくい方や、周りの音が大きくて気づきにくい環境にいる方にとって、専用の「お知らせグッズ」は日々の安心感をぐっと高めてくれます。
ここでは、シニアの方にぴったりの代表的なグッズとその特徴、選び方のポイントをご紹介します。
まず代表的なのが、置き型の着信ランプです。
スマホとつないでおくと、電話がかかってきたときに、強い光でピカピカっと知らせてくれます。
光はまっすぐ届くので、テレビを見ているときや、誰かとおしゃべりしているときでも、視界の端に入ってきて気づきやすいのが良いところ。
製品によっては、光る色や点滅パターンを変えられたり、特定の人からの電話だけ違う光り方に設定できたりもします。
(参考)スマホ着信音フラッシュコール(NZT-380-SP)
他にも、スピーカーでスマホの音そのもの大きくするのもおすすめです。
リビングはもちろん、防水なのでキッチンやお風呂周りでも使えるのがいいですね。
これらのグッズを導入するときは、失敗しないように以下の点を確認してみてくださいね。
- 光・振動・音のうち、どの感覚に一番気づきやすいか?
- いつもいる場所に置けるサイズや重さか?
- 光の明るさや振動の強さを調整できるか?
- 電気代や電池の持ちは大丈夫か?
- 使っているスマホに対応しているか?
設定変更だけでなく、便利なグッズも上手く活用していきましょう。
携帯電話の着信を光で知らせる
光でのお知らせは、耳の聞こえに頼らずに着信を知ることができる、とても確実な方法です。
特に、年齢とともに聞こえにくさを感じている方や、周りがにぎやかな場所にいることが多い方にとって、光は音よりも見逃しにくく、生活の安心感を大きく高めてくれます。
スマホ本体の機能と、外付けのグッズを組み合わせることで、家の中でも外出先でも、着信の見逃しを防ぐことができます。
まず、スマホ本体の機能として、iPhoneにはLEDフラッシュ通知が標準でついています。
これは、電話やメッセージが届いたときに、カメラのフラッシュライトを強くピカピカっと点滅させる機能です。
iPhoneの場合
「設定」→「アクセシビリティ」→「オーディオ/ビジュアル」→「LEDフラッシュ通知」をオン 出典:Apple
Androidのスマホでも、多くの機種に「フラッシュ通知」機能がついています。
「カメラライト通知」など、メーカーによって名前が少し違うこともあります。
また、一部の機種では画面全体がパッと明るくなる「画面フラッシュ通知」も使え、スマホを伏せて置いていても、光が周りに反射して気づきやすくなります。
本体の機能に加えて、外付けの光るグッズを使う方法もあります。
スマホと連携させておくと、着信時に強い光を放ちます。
こうした装置をリビングや寝室など、いくつかの場所に置いておけば、家のどこにいても光で着信に気づけます。
光るグッズを置くときは、「視界の端に入りやすい場所」や「壁や天井に光が反射しやすい場所」に置くのが効果的です。
また、強い光が苦手な方は、光の強さを調整できるタイプを選ぶと快適に使えますよ。
光のお知らせ機能を導入するときのチェックポイントをまとめます。
- スマホ本体に光る機能はあるか?設定はオンになっているか?
- 外付けのグッズを使うなら、自分のスマホに対応しているか?
- 光の強さや点滅パターンを調整できるか?
- 電源はコンセントか、USBか、電池式か?
音と光を組み合わせることで、着信に気づく確率はぐんとアップします。
特に耳が遠い方や、騒がしい場所で過ごすことが多い方は、ぜひ光の活用を検討してみてください。
高齢者・難聴向けの携帯電話
シニアや耳が遠い方向けに作られた携帯電話は、ただ「音が大きい」だけではありません。
聞き取りやすい音質への調整、シンプルな操作、見やすい画面など、年齢による体の変化にやさしく寄り添う工夫がいっぱい詰まっています。
例えば、NTTドコモの「らくらくホン」や「らくらくスマートフォン」シリーズは、相手の声がはっきり聞こえるようにする「はっきりボイス」機能がついています。
周りのザワザワした音を抑える機能や、相手の早口をゆっくりに変換してくれる機能もあり、聞こえにくさをしっかりサポートしてくれます。出典:NTTドコモ
ソフトバンクの「シンプルスマホ」シリーズも、大きな音と聞きやすい音質が特徴です。
着信時には画面全体がピカッと光ってお知らせ。初めてスマホを使う方でも、基本的な設定がまとめてできる「かんたん設定」メニューがあるので安心です。出典:ソフトバンク
auの「かんたんケータイ」や「BASIO」シリーズは、相手の声の高さを調整して聞きやすくする機能や、ゆっくり話してくれる機能がついています。防水・防塵で衝撃にも強いので、毎日安心して使えます。出典:au
スマホを選ぶときは、音の大きさよりも「聞き取りやすさ」が大切です。
お店で試すときは、実際に家族や店員さんと電話してみて、雑音が多い場所でも聞きやすいかを確認するのがおすすめです。
また、ボタンが大きくて押しやすいか、画面の文字が見やすいかといった操作のしやすさも重要なポイント。
これらのシニア向けスマホは、音・光・振動のお知らせ機能はもちろん、スマートウォッチなど他の機器と連携させることで、さらに気づきやすい環境を作ることもできます。
総務省の調査では、高齢者が携帯電話やスマートフォンを利用する際に「文字の小ささ」や「操作のしづらさ」などに不便を感じていることが報告されています。出典:総務省
これらの悩みを解決してくれるシニア向けスマホは、日々の安心感を高め、家族との大切なつながりを保つための、心強い味方になってくれますよ。
高齢者の電話聞こえない時の対策|スマホの選び方と活用法

- 耳が遠い人用の携帯電話|ドコモ
- 耳が遠い人用の携帯電話|ソフトバンク
- 耳が遠い人用の携帯電話|au
- 耳が聞こえない人向けの携帯電話サービスは?
耳が遠い人用の携帯電話|ドコモ
NTTドコモは、日本国内で最も多くの利用者を抱える移動通信事業者の一つであり、高齢者や耳が遠い方向けに特化した端末ラインアップを長年にわたって提供しています。
特に「らくらくホン」や「らくらくスマートフォン」シリーズは、単なるシニア向けモデルではなく、難聴や視覚・操作性の低下に対応するための工夫がされています。
音声面では、最大音量が一般的なスマートフォンより高く設定できるだけでなく、聞き取りにくい音を補正するはっきりボイス機能や、相手の声をより前面に出すボイスクリア機能が搭載されています。
これにより、駅や商店街などの騒がしい環境でも会話が聞こえやすくなり、聞き返しの回数を減らせます。
また、通話中に雑音を自動で抑制するノイズキャンセル機能も標準装備され、風切り音や周囲の環境音を低減します出典:NTTドコモ
操作性においても、物理キーのサイズや押しやすさに配慮されており、キー表面には微細な凹凸加工が施されているため、視覚に頼らずともボタン位置を把握できます。
画面上の文字やアイコンは大きく表示され、ホーム画面の構成もシンプルで直感的になっています。
誤タッチを防ぐためのタッチ感度調整機能も備え、手先の動きが不安定になっている方にも安心して使えるようになっています。
さらに、安全性を高めるための機能として、緊急時にワンタッチで発信できるワンタッチダイヤルや、周囲に危険を知らせる緊急ブザーも搭載されています。
特にひとり暮らしの高齢者にとって、こうした機能は迅速な通報や家族への連絡手段として、日常の安心感を大きく高めてくれます。
また、ドコモの強みは端末そのものだけではありません。
全国のドコモショップでは、高齢者向けの操作説明や初期設定サポートが充実しており、購入時には音量・通知設定の最適化、連絡先登録、文字サイズ調整などをスタッフが直接行ってくれる点も安心です。
特に着信音や通知音に関しては、利用者の聴力特性に合わせて音色や周波数帯を選定するアドバイスを受けられるため、機種購入後すぐに快適な環境で利用開始できますよ。
通信サービス面でも、らくらくスマートフォン専用のアプリやサポート窓口が用意されています。
例えば、専用の「らくらくコミュニティ」アプリを通じて、簡単な操作で家族や友人とメッセージ交換が可能です。
また、迷惑電話対策機能も充実しており、不審な番号からの着信時には画面上に警告表示が出るため、詐欺被害防止にもつながります。
端末選びの際は、ドコモの公式サイトや店頭で実機を確認し、以下のポイントをチェックしておきましょう。
- 最大音量時の聞き取りやすさ(音割れや歪みがないか)
- 自分に適した着信音や音色
- キーの押しやすさと反応の速さ
- 画面表示の見やすさ(フォントや配色)
- 緊急時の連絡・通報機能の有無
高齢者が携帯電話を利用する上で重視するポイントとして「音声の聞き取りやすさ」と「操作のしやすさ」がありますが、ドコモの高齢者向け端末は、この2つを重視した設計になっているため、耳が遠い方やスマホ操作に不慣れな方にとって非常に適した選択肢になります。
また、らくらくホンシリーズはバッテリー持ちの良さでも評価が高く、数日に一度の充電で済むため、充電忘れによる着信見逃しのリスクも減らせます。
耳が遠い人用の携帯電話|ソフトバンク
ソフトバンクが提供する「シンプルスマホ」シリーズは、耳が遠い方やスマートフォン操作に不慣れな方でも安心して使えるよう、音声・通知・操作性の3つを徹底的に調整したモデルになっています。
特に、着信に気づきやすくするための大音量スピーカーと、視覚的に知らせる画面点滅通知の組み合わせは、聴覚と視覚の両方を活用する通知システムとして高く評価されています。
音声機能では、最大音量が一般的なスマートフォンより大きく設定できるだけでなく、音質補正機能により、会話の中で重要な中音域(500〜2000Hz)を強調します。
加齢による難聴では高音域の聞き取りが難しくなる傾向がありますが、シンプルスマホは中音域と低音域をしっかりと響かせる設計で、言葉を聞き取りやすくします。
また、屋外や騒がしい場所でも聞きやすいよう、通話中に周囲の雑音を低減するノイズキャンセラー機能を搭載しています。出典:ソフトバンク
通知面では、着信時に画面全体が明るく点滅する機能が標準装備されており、音が聞き取りづらい環境でも一目で着信を確認できます。
さらに、バイブレーションの強度設定も可能で、手に持っていなくても机や棚を通じて振動が伝わるレベルに調整できます。
これにより、耳だけでなく手や目でも着信に気づきやすくなりますね。
操作性の面では、「かんたん設定」メニューを開くだけで、音量・音質・表示フォント・タッチ感度などの基本設定を一括で変更できる機能があります。
初めてスマホを使う方でも、細かな設定項目を探す手間なく、自分に合った状態に調整できます。
また、ホーム画面は大きなアイコンと文字で構成され、迷うことなく主要な機能にアクセス可能です。
安全面にも配慮されており、迷惑電話対策機能では不審な番号からの着信時に画面に警告が表示され、通話前に危険性を判断できます。
ワンタッチダイヤル登録により、家族や緊急連絡先を物理ボタンや画面上の大きなボタンから即座に呼び出せます。
このような機能があると、緊急時やとっさの連絡時にとても役立ちます。
さらに、ソフトバンクショップでは高齢者向けのサポートプログラムを実施しており、購入時に着信音の音色や周波数帯の調整、光通知の有効化、スマートウォッチや着信ランプとの連携設定などスタッフがサポートしてくれます。
こうした店舗での初期設定サポートがあると、設定の複雑と悩む高齢者ユーザーにとって心強いですね。
端末を選ぶときは、以下の点を店頭で実際に確認するのがおすすめです。
- 最大音量時の明瞭さ(音割れや歪みの有無)
- 画面点滅や光通知の見やすさ(まぶしすぎないか)
- バイブレーションの強度と体感度合い
- 「かんたん設定」での調整項目の網羅性
- ワンタッチダイヤルの登録・操作のしやすさ
音声以外に点滅や振動など、着信見逃し防止の工夫が多いので、耳が遠い方でも「確実に着信に気づき、安心して通話できる」ことを重視するのであれば、有力な選択肢になります。
耳が遠い人用の携帯電話|au
au(KDDI)が展開する「かんたんケータイ」や「BASIO」シリーズは、耳が遠い方やスマートフォンの操作に不安を抱く方でも快適に使えるよう、音声・表示・操作性の全方位で高齢者向けに工夫がされています。出典:au
特に通話時の聞き取りやすさを重視し、声の高さを補正する音声ピッチ補正機能や、相手の話す速度を自動的に遅くするゆっくり通話機能を搭載しています。
これにより、会話中に聞き逃した部分を再確認しやすく、情報の取りこぼしを防げます。
加齢による難聴では特定の周波数帯域が聞き取りにくくなるため、単純な音量増加だけでは解決できない場合があります。
「かんたんケータイ」や「BASIO」シリーズでは、通話音声の中音域(500〜2000Hz)を強調し、高音域はやや抑えて耳への負担を軽減します。
この調整は聴覚補助器(補聴器)と似た原理で、音量だけでなく音質を耳の特性に合わせるアプローチです。
着信時には、大音量スピーカーからの呼び出し音と同時に画面や背面のLEDが点滅し、強めのバイブレーションが作動します。
バイブレーションは強度調整が可能で、机上に置いたときでも振動が伝わる設計です。
さらに、防水・防塵性能(IPX5/IPX8・IP5Xなど)を備えているため、浴室や台所といった水回りでも安心して使用できます。
音以外に光や振動も利用して、着信に気づきやすい工夫がされています。
見やすさについては、大きくはっきりしたフォントと高コントラスト表示により、画面の明るさや色合いが外光下でも見やすく調整されています。
ホーム画面には大きなアイコンが並び、主要な機能にワンタッチでアクセスできるため、迷うことが少なくなります。
安全・安心機能としては、緊急時にワンタッチで家族や指定先に発信できる「ワンタッチダイヤル」や、防犯ブザー機能を搭載。
通話中には雑音を低減するノイズキャンセル機能が働き、屋外や混雑した場所でもクリアな音声を確保します。
また、迷惑電話対策として、不審な番号からの着信に警告表示を行う機能も備えています。
購入・設定時には、auショップで高齢者向けのサポートサービスを受けられます。
ここでは、音量・音質の最適化、LED通知の有効化、迷惑電話対策機能のオン設定、さらにはスマートウォッチや着信ランプなど外部機器との連携まで、生活環境に合わせたカスタマイズが可能です。
ドコモやソフトバンクと同様、サポート機能があるので初期設定も安心ですね。
端末を選ぶ際は、以下を確認しておきましょう。
- 音声ピッチ補正やゆっくり通話の効果(実際の会話での聞き取りやすさ)
- 最大音量時の音質(音割れや耳への負担の有無)
- 防水・防塵性能(洗面台やお風呂場などで使用する可能性はあるか)
- バイブレーションの強度と感触
- ボタンやアイコンの見やすさ・押しやすさ
耳が遠くてもストレスなく会話を楽しみたい、外出先でも安心して使いたいというニーズに応えるモデルとして有力な選択肢です。
耳が聞こえない人向けの携帯電話サービスは?
耳が全く聞こえない方や、聞こえが非常に困難な方に向けて、音声ではなく「文字」や「映像」でコミュニケーションをとるためのサービスがあります。
スマホ本体の機能と組み合わせることで、安心して連絡を取り合うことができます。
まず、国が整備した公的な仕組みとして「電話リレーサービス」があります。これは、手話通訳オペレーターや文字通訳オペレーターが間に入り、電話の相手とは音声で、ご本人とは手話や文字でやりとりをつないでくれるサービスです。
24時間365日利用でき、110番や119番といった緊急通報にも対応しているので、いざという時も安心です。
その他、以前はNTTドコモの「みえる電話」や「字幕電話サービス」など携帯キャリアが文字で会話を補助するサービスを提供していましたが、現在は終了しています。
代わりに、「ヨメテル」のようなスマートフォンアプリを活用する方法があります。
「ヨメテル」は、相手の話した言葉をリアルタイムで文字に変換してくれるアプリです。
電話はもちろん、対面での会話やテレビの音声なども文字で表示してくれるので、聞こえに不安がある方にとって心強い味方になります。
これらのサービスを使うときも、そもそも着信に気づけなければ意味がありません。
スマホの光や振動のお知らせ機能と組み合わせることで、「着信に気づく→サービスを使って会話する」というスムーズな流れを作ることが大切です。
サービス利用前に確認したいこと
- 自分のスマホで使えるか?(OSや機種の条件)
- 利用料金はかかるか?(無料や割引はあるか)
- 緊急通報はできるか?どうやってかけるか?
- 利用開始までに登録は必要か?
- プライバシーは守られるか?
高齢者の電話が聞こえない時の対策【スマホ設定・着信補助グッズ】徹底解説まとめ
- 年齢を重ねると、高い音から聞こえにくくなる傾向があります。
- 周りの生活音も、着信に気づきにくい原因の一つです。
- スマホの設定は、ご自身の状況に合わせ見直しましょう。
- 音量だけでなく、聞きやすい「音色」に変えてみるのが効果的です。
- スマホケースや置き場所が、音や振動を弱めている可能性があります。
- 「光」と「振動」をプラスして、複数の方法でお知らせしてもらいましょう。
- LEDフラッシュや画面の点滅を利用して、音以外でも着信がわかるようにしましょう。
- ご家族と一緒に「着信お知らせテスト」をして、最適な設定を見つけましょう。
- スマートウォッチなどを活用するのも一つの手段です。
- 「らくらくホン」など、シニア向けに作られたスマホは心強い選択肢です。
- スマホを選ぶときは、お店で実際に試して、音質や操作性を確認しましょう。
- 耳が聞こえない方向けに、文字や手話で通話できるサービスもあります。
- 「電話リレーサービス」は24時間365日、緊急時も利用できます。